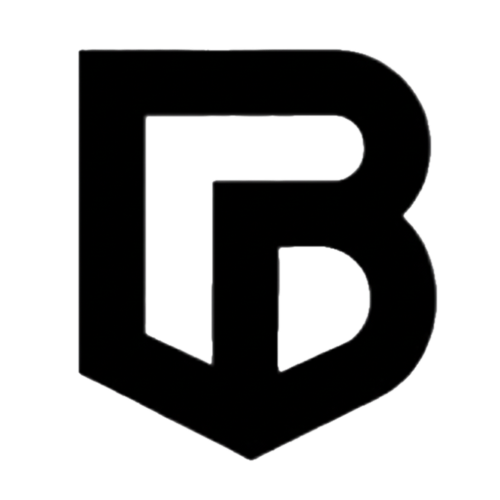日本の電子署名法と電子契約の法的効力:実務運用ガイド
コロナ禍を機に一気に普及した電子契約。収入印紙が不要、郵送の手間がゼロ、検索が容易などメリットは計り知れません。 しかし、「物理的なハンコがなくて、本当に法的に大丈夫なのか?」「裁判になった時に証拠になるのか?」という不安を持つ経営者や法務担当者もまだ少なくありません。
本記事では、日本の電子契約の法的根拠となる「電子署名法」の仕組みと、実務で安心して使うための運用ポイントを徹底解説します。
電子署名法とは?(法的根拠)
2001年に施行された「電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)」が、電子契約の法的効力を支えています。 最も重要なのは、第三条です。
電子署名法 第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
法律用語で「真正に成立したものと推定する」とは、「その文書は本人が自分の意思で作成した(偽造されたものではない)と裁判所が一応認める」という意味です。 つまり、要件を満たす電子署名は、実印を押した契約書と同等の証拠能力を持つのです。
「当事者型」と「立会人型」の違い
電子署名には大きく分けて2つのタイプがあり、法的効力の担保の仕方が異なります。
1. 当事者型(実印タイプ)
- 仕組み: 利用者本人が、認証局(第三者機関)から発行された「電子証明書(ICカードやUSBトークンなど)」を取得し、それを使って署名する。
- メリット: 本人確認の厳格性が非常に高く、法的効力が最も強い。「本人による電子署名」の要件を完全に満たします。
- デメリット: 相手方も電子証明書を取得する必要があり、導入ハードルが高い。
- 主な用途: 不動産登記、巨額の融資契約など、極めて重要度の高い契約。
2. 立会人型(認印タイプ)
- 仕組み: 利用者は電子証明書を持たず、クラウドサービス事業者(立会人)がメールアドレス認証などで本人確認を行い、事業者の電子証明書を使って代理で署名する。
- メリット: メールアドレスさえあれば誰でも利用でき、相手方の負担が少ない。現在の電子契約サービスの主流(DocuSign, CloudSign, Adobe Signなど)。
- デメリット: 当事者型に比べると、理論上の本人確認レベルは下がる。
- 法的解釈: 長らく「本人による電子署名」に該当するか議論がありましたが、2020年の政府見解(Q&A)により、メール認証や二要素認証などで十分な本人確認が行われていれば、電子署名法三条の推定効が及ぶと解釈が明確化されました。
「なりすまし」リスクへの対策
電子契約で最も懸念されるのが、「他人が勝手にメールを受信してクリックしてしまう」などの「なりすまし」です。これを防ぐために、実務では以下のような対策(多要素認証)を組み合わせるのが一般的です。
- メール認証: 指定したメールアドレスにリンクを送り、アクセスできることを確認(基本)。
- アクセスコード(パスワード): 別途電話やSMSでパスワードを伝え、入力しないと署名できないようにする。
- SMS認証: スマートフォンのSMSに認証コードを送る。
- 本人確認書類のアップロード: 免許証などの画像をアップロードさせる(eKYC)。
タイムスタンプの重要性
電子署名とセットで重要なのが「タイムスタンプ」です。
- 電子署名: 「誰が」作成したか、「改ざんされていないか」を証明。
- タイムスタンプ: 「いつ」その文書が存在していたか、「その時刻以降に改ざんされていないか」を証明。
この2つが組み合わさることで、完全な証拠能力が担保されます。主要な電子契約サービスでは、署名完了時に自動的に認定タイムスタンプが付与される仕組みになっています。
電子契約が使えないケース
法改正によりほとんどの契約書が電子化可能になりましたが、一部例外があります(2025年現在)。
- 公正証書が必要な契約: 事業用定期借地権設定契約、任意後見契約など。これらは公証人の面前で作成する必要があります(ただし、公証手続きの電子化も進んでいます)。
- 書面交付義務がある一部の契約: 訪問販売等のクーリングオフ書面など(消費者の承諾があれば電子交付可能になっています)。
最新の法改正状況を常に確認することが重要です。
まとめ
電子契約は、適切なサービスを選び、適切な運用(多要素認証など)を行えば、紙の契約書と同等、あるいはそれ以上の安全性と証拠能力を持ちます。 何より、契約締結スピードの向上と印紙税削減のメリットは圧倒的です。まだ導入していない企業は、これを機に検討することをお勧めします。